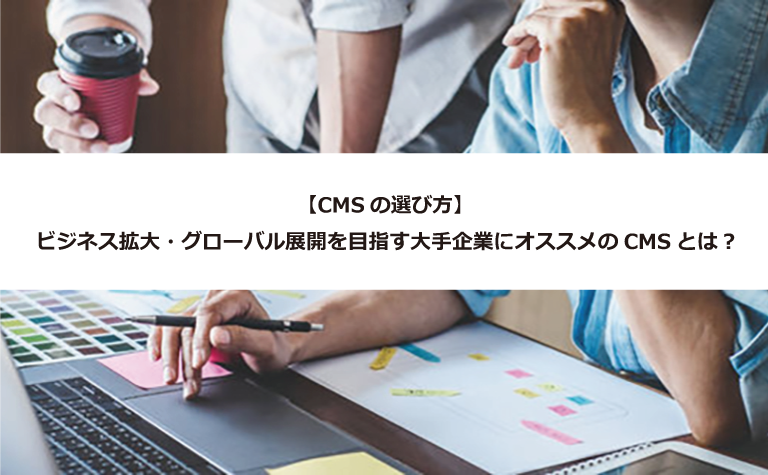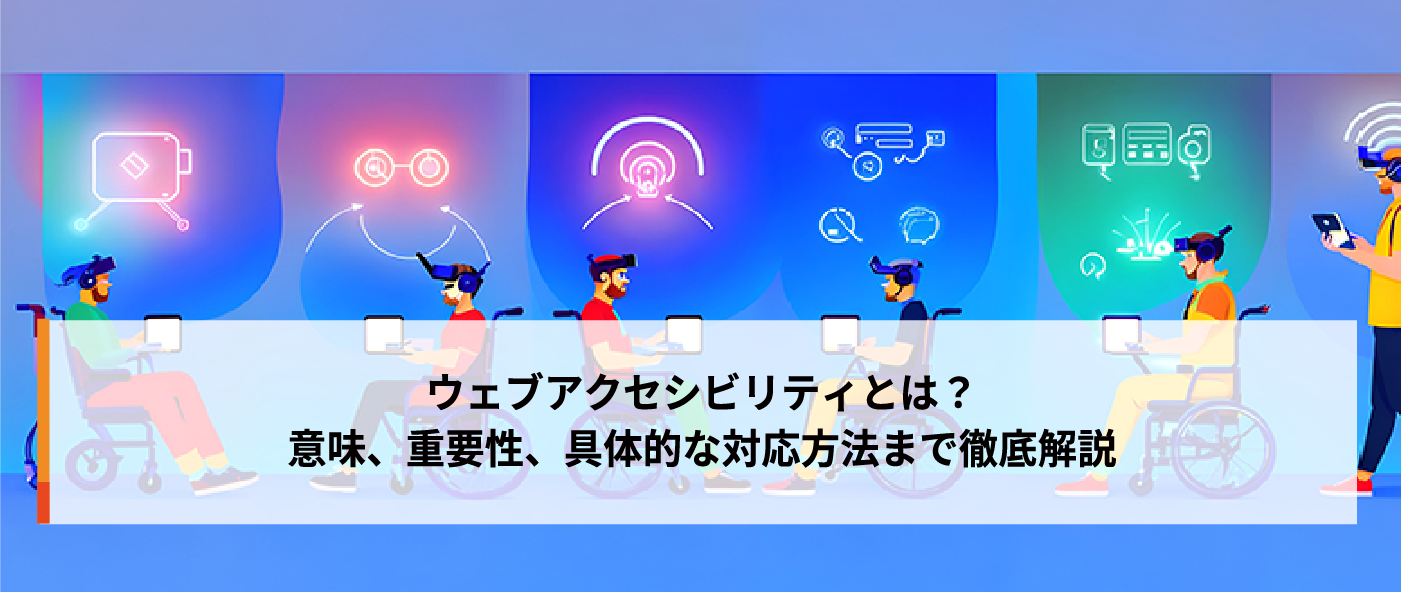


2025.07.16
ウェブアクセシビリティとは?意味、重要性、具体的な対応方法まで徹底解説
ウェブアクセシビリティとは何か、その意味からJIS規格、WCAG達成基準、具体的な対応方法、2024年施行の法改正(合理的配慮の義務化)までを専門家が分かりやすく解説します。企業の信頼性向上と機会損失の防止に繋がる、ウェブアクセシビリティ対応の第一歩を始めましょう。
目次
1. ウェブアクセシビリティの基本:すべての人がウェブサイトを快適に利用するために >>
- ・ウェブアクセシビリティの公的な規格「JIS X 8341-3」 >>
- ・世界的なガイドライン「WCAG 2.1」とは >>
- ・2024年4月施行「改正障害者差別解消法」と合理的配慮の提供義務化 >>
- ・【HTML編】今すぐできる実装例 >>
- ・【デザイン編】配色のコントラスト比やフォントサイズの考慮
- ・【コンテンツ編】分かりやすい言葉遣いと明確な指示 >>
- ・【具体例】実際のWebサイトでウェブアクセシビリティへ対応した例 >>
- ・STEP1:方針の策定と公開(アクセシビリティポリシー) >>
- ・STEP2:対象範囲の決定と目標レベルの設定 >>
- ・STEP3:ウェブアクセシビリティツールを活用した現状把握と最適化 >>
- ・STEP4:上記の対応から逸脱しない運用・更新ガバナンスの決定 >>
- ・STEP5:継続的な改善とフィードバックの収集 >>
昨今、企業のDX推進が加速する中で「ウェブアクセシビリティ」の重要性が急速に高まっています。高齢者や障害を持つ方を含め、誰もがWebサイトやアプリの情報を快適に利用できる環境を整えることは、企業の社会的責任であると同時に、ビジネスチャンスの拡大にも繋がる重要な取り組みです。
この記事では、ウェブアクセシビリティの基本的な意味から、国内外の規格、2024年4月に施行された法改正の内容、そして今日から始められる具体的な対応方法まで、分かりやすく解説します。
ウェブアクセシビリティの意味とは?
ウェブアクセシビリティとは、年齢や身体的な条件、利用している環境(PC、スマートフォン、支援技術など)に関わらず、すべての人がWeb上で提供される情報やサービスを平等に利用できる状態を指します。「アクセシビリティ(accessibility)」という言葉が「接近できること、利用しやすさ」を意味するように、Webサイトへのアクセスにしやすさを保証する考え方です。
例えば、以下のような状況にある人々にとって、ウェブアクセシビリティは特に重要です。
なぜ今、ウェブアクセシビリティが重要視されるのか?
ウェブアクセシビリティが重要視される背景には、大きく分けて「社会的な要請」と「ビジネス上の必要性」の2つがあります。
ウェブアクセシビリティがもたらす企業側のメリット
ウェブアクセシビリティへの対応は、単なるコストや義務ではありません。企業にとって多くのメリットをもたらします。
ウェブアクセシビリティには、準拠すべき公的な規格や法律が存在します。
ウェブアクセシビリティの公的な規格「JIS X 8341-3」
「JIS X 8341-3」は、日本のウェブアクセシビリティに関する国家規格です。正式名称は「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」で、ウェブサイトを制作する際の具体的な指針が定められています。
この規格には、達成すべき基準のレベルとして「A」「AA」「AAA」の3段階があり、多くの企業サイトではレベル「AA」への準拠を目標としています。

JIS X 8341-3:2016 達成基準 早見表(レベルA & AA)より
https://waic.jp/resource/jis-x-8341-3-2016/
世界的なガイドライン「WCAG 2.1」とは
「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」は、Web技術の標準化を推進するW3Cが策定した、世界的なウェブアクセシビリティのガイドラインです。JIS X 8341-3も、このWCAGと技術的に同等になるよう策定されており、実質的な世界標準と言えます。
2024年4月施行「改正障害者差別解消法」と合理的配慮の提供義務化
2024年4月1日に施行された「改正障害者差別解消法」により、民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が、努力義務から法的義務へと変わりました。
これにより、障害のある人から「スクリーンリーダーで読み上げられないのでテキストで情報を提供してほしい」といった申し出があった場合、事業者は過重な負担にならない範囲で対応する義務を負います。ウェブサイトがアクセシブルでない場合、この合理的配慮の提供が困難になる、あるいは頻発する可能性があり、事前のウェブアクセシビリティ対応が極めて重要となっています。
| 行政機関等 | 事業者 | |
|---|---|---|
| 不当な差別的取り扱いの禁止 | してはいけない(義務) 第7条第1項 |
してはいけない(義務) 第7条第1項 |
| 合理的配慮の提供 | しなければならない(義務) 第7条第2項 |
するように努力(努力義務) → 令和6年4月1日から義務 第8条第2項 |
| 環境の整備 | するように努力(努力義務) 第5条 |
するように努力(努力義務) 第5条 |
※内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」をもとに作成した表
ここでは、今日からでも取り組める具体的な対応方法をいくつかご紹介します。
【HTML編】今すぐできる実装例
【デザイン編】配色のコントラスト比やフォントサイズの考慮
【コンテンツ編】分かりやすい言葉遣いと明確な指示
【具体例】実際のWebサイトでウェブアクセシビリティへ対応した例
体系的にアクセシビリティ対応を進めるためのステップと、便利なツールをご紹介します。
STEP1:方針の策定と公開(アクセシビリティポリシー)
まず、組織としてウェブアクセシビリティにどのように取り組むのか、方針を策定し、「ウェブアクセシビリティ方針」としてサイト上で公開します。目標とする適合レベル(例:JIS X 8341-3のレベルAA準拠)や対象範囲などを明記します。
STEP2:対象範囲の決定と目標レベルの設定
すべてのページを一度に対応するのが難しい場合は、優先度の高いページ(トップページ、主要なサービスページなど)から段階的に対応を進める計画を立てます。
STEP3:ウェブアクセシビリティツールを活用した現状把握と最適化
専門家による診断・対応が理想的ですが、ウェブアクセシビリティ最適化ツールを使って、自社サイトの現状把握と最適化をすることもできます。
世界的に多くの企業で導入されているウェブアクセシビリティツール「UserWay」は、Webサイトのウェブアクセシビリティ最適化を支援するツールです。国際パラリンピック委員会の公式サイトやグローバルで活躍する企業のWebサイトなどでもUserWayが導入され、障害のある人々がWebサイトを利用しやすくなっています。これにより、デジタル格差を軽減し、多くの人々のデジタル活用をサポートします。
STEP4:上記の対応から逸脱しない運用・更新ガバナンスの決定
アクセシビリティ品質を維持していくための運用・更新ガイドラインを順守してコンテンツを更新する必要があります。自社内でコンテンツ制作する際はもちろん、コンテンツ制作を外注する際のチェックフローなども予め決めておくと良いでしょう。
STEP5:継続的な改善とフィードバックの収集
ウェブアクセシビリティは一度対応すれば終わりではありません。サイトの更新に合わせて継続的にチェックを行うとともに、お問い合わせフォームなどを設置し、利用者からのフィードバックを収集・反映できる体制を整えることが重要です。
ウェブアクセシビリティへの対応は、もはや「やさしさ」や「思いやり」といった任意のものではなく、すべての企業に求められる社会的責務であり、ビジネスを成長させるための重要な投資です。
本記事でご紹介した内容を参考に、まずは自社サイトの現状把握から始めてみてはいかがでしょうか。すべての人にとって使いやすいWebサイトを実現することは、必ずや企業の信頼性を高め、新たな価値創造に繋がるはずです。